 Writing / quinn.anya
知人のブログを読んでいて、普段は柔らかい印象の女性なのに、ブログだと断定的(~だ。~である。等)な文体で、ちょっと違和感あるな~と思いまして。
じゃあ自分のブログはどうなのよ?と思って、いろいろ調べて&考えてみました。
いやはや、日本語って奥が深い…!
●常体(「である」調)と敬体(「です・ます」調)を混ぜない
コレはさすがに基本ですよね。小学校で習ったような気がします。
何で混ぜないほうが良いのかというと、会話に置き換えてみると分かりやすいと思います。
誰かと会話していて、相手の態度がコロコロ変わったら、どう思いますか?
ワタシなら、かなり怪しむというか、違和感を覚えます。
それと同様、「である」調と「です・ます」調が混ざった文章は、書き手の態度がコロコロ変わるように違和感があるのではないでしょうか。
Writing / quinn.anya
知人のブログを読んでいて、普段は柔らかい印象の女性なのに、ブログだと断定的(~だ。~である。等)な文体で、ちょっと違和感あるな~と思いまして。
じゃあ自分のブログはどうなのよ?と思って、いろいろ調べて&考えてみました。
いやはや、日本語って奥が深い…!
●常体(「である」調)と敬体(「です・ます」調)を混ぜない
コレはさすがに基本ですよね。小学校で習ったような気がします。
何で混ぜないほうが良いのかというと、会話に置き換えてみると分かりやすいと思います。
誰かと会話していて、相手の態度がコロコロ変わったら、どう思いますか?
ワタシなら、かなり怪しむというか、違和感を覚えます。
それと同様、「である」調と「です・ます」調が混ざった文章は、書き手の態度がコロコロ変わるように違和感があるのではないでしょうか。
Aの文章だと、校正不足というか、記述ミス?という印象を持ちますよね。 例外はありますが、基本的に文体はブログ全体で揃えたほうが良さそうです。 ※例外=見出し/箇条書きただし、1つの箇条書きの中では1つの文体に統一)/引用文のような挿入された文章など例) A. 敬体・常体混じり 私たちは、毎日のようにカウンセリングの勉強をしています。 なぜなら、求職者の方の期待に応えるためには、自己研鑚が欠かせないからだ。 B. 常体に統一 私たちは、毎日のようにカウンセリングの勉強をしている。 なぜなら、求職者の期待に応えるためには、自己研鑚が欠かせないからだ。 C. 敬体に統一 私たちは、毎日のようにカウンセリングの勉強をしています。 なぜなら、求職者の期待に応えるためには、自己研鑚が欠かせないからです。
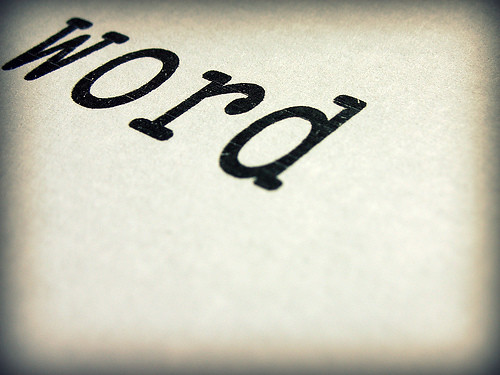 Blog Marketing Up Close Word Blog Graphi / Maria Reyes-McDavis
●文体が与える印象
文体を統一したほうが良いのは分かりました。
では、それぞれの文体には、どんな特徴があるんでしょうか。
Wikipedia先生に聞いてみました。
Blog Marketing Up Close Word Blog Graphi / Maria Reyes-McDavis
●文体が与える印象
文体を統一したほうが良いのは分かりました。
では、それぞれの文体には、どんな特徴があるんでしょうか。
Wikipedia先生に聞いてみました。
ふむふむ。 確かに、論文や議事録は、常体で書かれることが多いですよね。 ワタシなりに、それぞれの文体のメリット・デメリットを考えて、整理してみました。 <常体> ・メリット=明快な印象。論理的な文章に向いている。 ・デメリット=一方的(受け手によっては高圧的)な印象。 <敬体> ・メリット=親近感が沸く(子どもでも読みやすい)。語りかけられるような印象。 ・デメリット=回りくどくなる(文章が長くなる)傾向がある。日本語の文体は、大きく普通体(常体)および丁寧体(敬体)の2種類に分かれる。 (中略) 普通体は相手を意識しないかのような文体であるため独語体と称し、丁寧体は相手を意識する文体であるため対話体と称することもある。(Wikipedia「日本語」>「文体」の項より抜粋)
 With A Megaphone By A Wall / garryknight
●まとめ
どちらが良い・悪いというわけではありませんが、ブログは読んでくださる方がいてこそのモノだと思っているので、「対話体」とも呼ばれる「です・ます」調が良いのかなと思いました。あくまで、ワタシの場合ですが。
たまに敬体ではない文が混ざったりしますが、実はコレ、ちゃんと意識して書いてるんですよ~。
独り言っぽく、「~じゃないかな…」とか、「~なんだけどなー」とか(でも、コレって「常体」なんだろーか。。)
あと、常体でも全然一方的な印象を与えない文も存在しますよね。
たちさん(@ttachi)のブログ、「No Second Life」が分かりやすい例かと思うんですが、基本的に「である」調なのに、全然一方的な印象を受けません。
ご本人を直接知っているからかもしれませんが、常体・敬体というより、口語調?な感じがします。
うーむ、ワタシの独り言っぽい文も、口語調なのかしら。
ではまた!
話し言葉では、「敬語はココロの距離」と思っている踊るOL(@jaggyboss)でした!
With A Megaphone By A Wall / garryknight
●まとめ
どちらが良い・悪いというわけではありませんが、ブログは読んでくださる方がいてこそのモノだと思っているので、「対話体」とも呼ばれる「です・ます」調が良いのかなと思いました。あくまで、ワタシの場合ですが。
たまに敬体ではない文が混ざったりしますが、実はコレ、ちゃんと意識して書いてるんですよ~。
独り言っぽく、「~じゃないかな…」とか、「~なんだけどなー」とか(でも、コレって「常体」なんだろーか。。)
あと、常体でも全然一方的な印象を与えない文も存在しますよね。
たちさん(@ttachi)のブログ、「No Second Life」が分かりやすい例かと思うんですが、基本的に「である」調なのに、全然一方的な印象を受けません。
ご本人を直接知っているからかもしれませんが、常体・敬体というより、口語調?な感じがします。
うーむ、ワタシの独り言っぽい文も、口語調なのかしら。
ではまた!
話し言葉では、「敬語はココロの距離」と思っている踊るOL(@jaggyboss)でした!